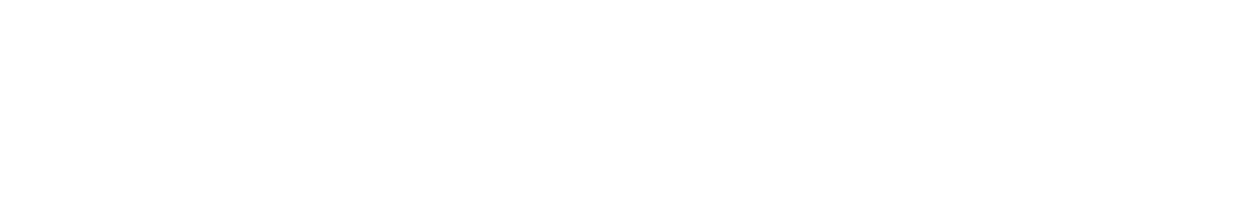映画製作とファンづくり、マーケティング、資金調達の新たなカタチを提示する「映画ST(セキュリティー・トークン)」。2025年公開予定の映画『宝島』では、STを活用した映画製作/投資モデルが導入され、映画製作陣と投資家がこれまでにない一体感を生み出しました。本記事では、映画ST『宝島』プロジェクトを手がけたフィリップ証券株式会社 代表取締役社長兼CEOの永堀真氏と、Securitize Japan株式会社 カントリーヘッド 小林英至が対談。映画STの可能性と、その先に見据える未来について語ります。

※映画『宝島』とは?
直木賞受賞作の実写化映画『宝島』(2025年9月公開予定、日米共同製作、監督:大友啓史、出演:妻夫木聡、広瀬すず など)では、映画製作委員会への出資で得られる権利をST化。フィリップ証券が組成・販売、SecuritizeがST基盤を提供。投資家は映画STに投資することで、映画の興行収入等から得られる配当とは別に、映画エンドロールへの名前の記載や、限定イベントなどへの招待といった特典を得ることができる。製作者としては、資金調達とマーケティングを同時に行えるというメリットも。従来の「一方的に観る」時代から「製作者と支援者が一緒になって創り育てる」時代となり、一つの情報媒体として重要視されているSNSなどを通じて支援者が製作者の立場から発信したり、自らの手でファン・マーケティングを行なう時代へと変化していく象徴的な事例になると期待されている。
映画ST『宝島』が生んだ製作陣と投資家の一体感
小林:今日は映画STについて、永堀さんと語っていきたいと思います。まずはどのような経緯でST、なかでも映画STに取り組むことになったのかを教えてください。
永堀氏:投資をもっと身近にしたいという想いがずっとあるのですが、身近にする方法のひとつがSTなのではないかと感じていました。単に収益を追いかける賭け事に近い枠組みではなく、多くの人が「応援・支援」という投資本来の姿に参加していくイメージが、STだと具体的に湧いてきたのです。投資をもっと身近に感じて頂くことで、資金が循環するエコシステムをつくっていきたい。日本人のDNAに「助け合いの精神」がありますから、応援・支援の投資は日本人の気質とも合っていると思います。
2022年3月頃だったと思いますが、映画『宝島』で制作プロダクションを担当しているクロスメディアの佐倉寛二郎さんとランチをしていて今回の映画STのプロジェクトがスタートしました。佐倉さんには「映画産業は残していかなければいけない一つの大切な文化である。その想いを共感した方々が支援し、参加できる形をつくっていきたい」、その上で「まずは大手法人が委員として参加している大作映画の投資枠を抑えて提供したい」と仰っていただきました。
これを経て、多くの方々に映画STというものが浸透すれば、もっと多様なことに共感・応援できるシステムを創り上げられると考えました。
例えば、地元でつくられた作品を応援したい。新進気鋭の監督や若手俳優を応援したい。そんな想いに、映画STは応えられるのではないでしょうか?作品や監督、俳優が育っていくプロセスに携わることができるのは、映画STならではの魅力だと思います。
小林:従来の映画を「一方的に観る時代」から、「製作陣と投資家・支援者が一緒になって創り育てる時代」への移行ですね。『宝島』のプロジェクトを進める中で、新しい発見はありましたか?
永堀氏:株式などの証券投資とは異なる投資家層が多いと感じました。一般的に投資家はリターン、パフォーマンスを重視しますが、映画STではそれだけでなく、むしろ推し活的な要素が強く、新しい挑戦を応援したい、映画製作をサポートしたいという想いを持った投資家の方々が多かったですね。映画や芸術、文化に対する想い、エンタメへの造詣、新しい挑戦への支援といった熱量を感じることができました。これは、金融だけの投資ではない世界観だと思います。投資家のなかには、「会社と家の往復の人生のなかで、違った体験をしてみたい」という方もいらっしゃいました。映画STは、人生を豊かにすることができる投資ではないかと考えております。
小林:『宝島』では、投資家限定の1日ツアーを企画したそうですね。
永堀氏:はい。1口以上の投資で参加可能な企画でした。大友監督にご挨拶できるチャンスもいただき、とても貴重な体験になったと思います。『宝島』の製作委員幹事で電通の五十嵐真志プロデューサーがSTにとても理解のある方で、「投資家のみなさんも製作者の仲間だから」と映画の裏話、キャスト選定の裏話などを投資家限定で話してくださいました。新型コロナの影響で2回撮影が延期したのですが、それをどう乗り越えたかも話してくれました。製作の裏側の人の話を直接聞けたので、投資家のみなさんの満足度も高く「製作者のファンになった。」「この映画をたくさんの方々に観て頂けるように自分が出来る限りのことをしたい。」という声もありました。ファンミーティングが飲み会に発展したり、プロジェクトが発足した当初は想定していなかったことも投資家の方々の熱意のお蔭でたくさん実現できました。
製作陣からどんどん投資家に近づいてくれて、とても一体感があるプロジェクトだったと思います。「自分たちになにかやれることはないか?」と、みんなが積極的で、製作サイドと投資家サイドなど、「どっちサイド」じゃなく、垣根がないところがとてもブロックチェーン・web3的な共創の現場だったのではないかと。
「ボランティアをやりたい」という投資家の方も出てきて、「でも、ボランティアってなにができるんだろう?」というのも、みんなで考えたんですね。投資家層が、一般的な投資家とはやはり全然違います。「一体感」「参加感」があるのが映画STの特徴で、映画をつくりたかった、映画に関わりたい、映画界を変えたいという投資家の方もいらっしゃったり、多様な投資動機があることも映画STならではです。アンケートをお願いしても半数以上が回答してくださいますし、協力的な投資家が多く、映画業界のことをわかって投資してくださっていると感じました。投資の本来の姿である「応援」「支援」の精神、その大切さを改めて実感できました。映画の完成も嬉しいですし、エンドロールに自分の名前が刻まれるというのも、やはり嬉しいことですね。
Securitizeを選んだ理由
小林:フィリップ証券がSecuritizeを選んでくださったのには、どのような理由があったのでしょうか?
永堀氏:パートナーに選ばせていただいたのは、グローバル展開している企業であり、パブリックチェーンも扱っているからです。長期的な視点でST市場を発展させるためには、パーミッションド(ノンパブリック)に限定せず、オープンな市場での展開が重要であると考えています。日本だけではなく、今後はアジア展開、世界展開を考えているため、長期的なパートナーとしてSecuritizeさんがベストと判断しました。今後はパブリックチェーンが世界の潮流だと思います。新しいチャレンジは簡単ではありませんが、苦楽をともにして長いお付き合いをしていけるパートナーを選びました。映画STなどのセカンダリーマーケットも、今後は展開していきたいですね。
小林:ST市場はまだ過渡期ですが、いずれはパブリックチェーンを活用し、P2Pに近いモデルへと進化していくべきだと思います。STでパブリックチェーンを使うことはグローバル・スタンダードと言えます。フィリップ証券とも、パブリックチェーン前提でのST市場を牽引する新しいプロジェクトを成功させていきたいですね。

映画STの認知拡大が課題
小林:『宝島』のプロジェクトを経験して、課題と感じていることにはどんな点がありますか?
永堀氏:映画STは、新しい概念です。STの浸透もまだ進んでいないなかで、映画公開の1年以上も前から資金調達を進めるのは大きなチャレンジでした。映画自体の認知がない段階でSTO(セキュリティ・トークン・オファリング)を行うことの難しさも実感しました。STの啓蒙活動は、まだ必要であると感じます。一方で、少しずつSTの認知が拡大してきたとも感じていて、不動産でのSTの活用などの影響でST自体は広まりつつあると思います。『宝島』が映画STの先行事例となり、今後、映画STが普及したときに良い効果を生んでくれるのではないかと期待しています。
STの特徴のひとつに、「投資家と事業会社との距離が近いこと」があると思います。事業者、顧客、投資家が明確に分離しているわけではなく、顧客にもSTへの投資に興味を持っていただける。STによって、その事業会社にとって、真の意味でのロイヤルカスタマーになって頂ける可能性が高まるという特徴があります。BtoCの関係づくり、関係の深化にSTは有効です。映画とSTはとても相性が良く、なるべくしてなった、STが進むべき方向であると感じています。
STは文化と金融をつなぐエコシステム
小林:投資家との距離の近さを活かして、参加するみんなが有形・無形のメリットを得られる絵を書けることがSTの良さかもしれませんね。
永堀氏:そうですね。映画以外にも、ミュージックアーティストやタレント、音楽家、画家、現代アートや伝統文化…など、応援したい対象はもっとあるはずです。映画STからエンタメST、文化STなど広げていきたいですね。今まで、付加価値が非常に高いのにスポットライトが当たりにくかった作品や創作家の方々にも、このサービスを通じてサポートさせて頂きたいと、『宝島』のプロジェクトを通じて改めて思いました。映画や芸術だけでは生活ができないので、会社員やアルバイトをしているという人もたくさんいます。生業として成り立たせるためにSTで応援できれば、良い作品がもっと世の中に生まれることになります。私たちも直接金融の担い手として、STでできることがあるのではないかと常に考えています。映画製作や作品づくりにいろいろな人が参加し、資金がちゃんと集まり循環する仕組みをつくりたいと考えています。
映画ST1号案件の『宝島』の経験を活かし、今後はさらに多くの支援者を巻き込んでいきたいです。なにかを応援、支援しながら投資する世界、エコシステムを絶やすことなくSecuritizeさんとともに広めていきたいですね。映画STは、資金調達の手段だけではなく、ファンを巻き込み、仲間を増やし、文化を支える仕組みです。STを活用することで、日本の文化やエンタメをさらに発展させていけると確信しています。